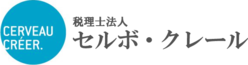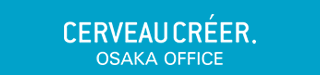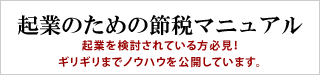IFRS適用の財務諸表上のインパクト
2017/11/01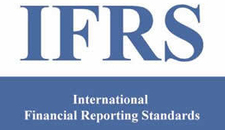
IFRSを適用することを検討する際に、どのような財務諸表上のインパクトがあるかはやはり気になるところだと思います。
IFRSを適用し、初めてIFRSによる財務諸表を公表する時、初度適用の注記といって、BSは過去2期、PLは過去1期の日本基準の財務諸表数値とIFRSの財務諸表数値の差異分析の注記を行います。その初度適用の注記を約30社ほどPLインパクトを見てみましたが、8割程度の会社がIFRS適用することによって利益を増加させています。中には日本基準の当期純利益の2倍以上も利益を増加させている会社もありました。
適用する会社によっては、たくさんのIFRS修正を行っている会社もありますし、ほとんどIFRS修正がない会社もあります。
市販のIFRSに関する書籍等を見ても、どのような分野で基準差異があるかは網羅的に紹介しているものの、実際導入するにあたってどの分野にインパクトがあるのかはあたりをつけておきたいところだと思います。私が行ってきたIFRS実務の主観や、他社事例を見た実感に基づくものではありますが、一般的に損益インパクトが大きいと思ったIFRSと日本基準の差異を紹介します。
(1)のれんの非償却
今更説明の必要はありませんが、やはり最もインパクトが大きいのはのれんの非償却です。なんだかんだ言っても、これ目的でIFRS適用を目指す会社もあると思います。
しかし、IFRSではのれんの減損損失も計上されやすいので注意が必要です。これは、のれんは非償却である一方、毎期、必ず減損損失を行うべきかどうか減損テストを行う必要があり(日本基準では2期連続赤字の場合など減損の兆候がある場合のみ減損テストを行います)、IFRSの基準が要求する減損テストの計算プロセスが日本基準の計算プロセスよりも減損損失が計上されやすい構造になっているからです。
のれんの減損損失が計上されるとなれば、非常に多額の損失が計上されるでしょうし、しかもIFRSに特別損益の考え方はありませんので、のれんの減損損失は営業損益に含まれることにも注意すべきです。
(2)退職給付関係
確定給付の退職給付制度は大きな損益インパクトが生じる可能性があります。
まず、数理計算上の差異の処理が日本基準と大きく異なります。日本基準においては数理計算上の差異は、発生時にその他の包括利益に全額認識した後、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数等で組替調整を行うことにより退職給付費用としてPLに計上されますが、IFRSではこの組替調整がありません(ちなみに発生時にその他の包括利益で認識したあとは、当該その他の包括利益額を利益剰余金に振り替えているケースが多いです)。数理計算上の差異が不利差異が多い場合、これはPL的にプラス方向です。
また、過去勤務債務が発生した際は、日本基準において過去勤務債務は数理計算上の差異に準ずる処理を行いますが、IFRSでは過去勤務債務は発生時に全額損益処理を行います。これはPL的にはマイナス方向のケースが多いとお思います。
退職給付会計にもない発生する利息費用についても基準差異があります。まず、割引率が日本基準と異なる可能性があります。また、日本基準では年金資産に期待運用収益率を乗じることによって期待運用収益を計算しますが、IFRSでは割引率を乗じて期待運用収益を計算します。一般的には、割引率の方が期待運用収益率よりも低いケースが多いため、結果的に期待運用収益は日本基準より少なくなり、結果、PL的にはマイナス方向である場合が多いと思います。
以上のように、それぞれの会社の退職給付の状況により異なるものではありますが、私の経験したケースでは、数理計算上の差異を組替調整しないことによりPL計上されなくなる影響が最も大きく、IFRSを適用することにより有利に働いた、というイメージです。
(3)開発費
日本基準では全て費用処理される研究開発費ですが、IFRSでは基準が要求する要件を満たし、資産性があると認められる開発費は資産計上します。費用が繰り延べられますので、PL的にはプラス方向です。
基準が要求する要件とは、かいつまんでいうと新製品の開発の過程で、その開発が成功することによって、その製品が将来販売され、かつ、販売されることにより会社に利益を確実にもたらすと見込まれることです。その見込みが立てば、それ以降、開発活動が終了するまでに発生した開発費は資産計上され、一定期間で償却することになります。
この基準、会社の行なっているビジネスの特性や、実務上の困難性など様々な要因があって、実際に資産計上している会社は多くないかもしれませんが、それらをクリアして資産計上した会社の中には、利益をかなり押し上げているところも見受けられます。
なお、それ以外の一般的な日本基準とIFRSの基準差異として、以下のものを挙げておきますが、これらに関しては企業によっても異なるかと思いますが、BS計上額は大きな影響があるものの、PLに対する影響は少ない印象です。というのも、IFRS適用においてはIFRS財務諸表を初めて開示する期の2期前に、IFRS最初のBSである開始財政状態計算書を作成するのですが、そこでIFRSに基づく資産、負債額を計上します。そのため、例えば有給負債など、人員数、給与水準に大きな変動がなければ、年度間において負債額に大きな変動が生じないものについては、PL計上額はそれほど大きなものにならない結果になるためです。
・有給休暇
有給休暇負債の計上が必要となるのもよく知られた論点と思いますが、前述したように有給休暇負債をいざ毎期算定してみると、それほど大きな変動がない場合があると思います。そのような場合、当該負債の差額がPLに計上されますので、影響は小さいです。
・繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性の検討については、①いわゆる5分類の判断基準がIFRSにはない、という論点と、②連結において関係会社間取引に基づく棚卸資産の未実現利益利益控除に適用する税効果について、繰延税金資産の回収可能性を日本基準では売却元の回収可能性で判断しますが、IFRSでは売却先の回収可能性で判断するという論点があります。
①はどちらかというと、繰延税金資産計上額が大きくなることが多いと思いますが、②については、企業ごとの状況によりケースバイケースです。
・収益の認識基準
日本基準でもIFRSに合わせた収益認識に関する会計基準が公表されましたが、IFRS適用においては収益計上の見直しが必要になる場合があります。端的に、代表的なものとして日本基準は出荷基準、IFRSでは着荷基準というのがあります。この論点、手間はかかりますが。毎期出荷、着荷の時期的差異が一定だとすると、PLインパクトはさほどない印象です。また、自社が顧客に対して当事者として取引するのではなく、いわゆる代理人として取引している場合は、売上と原価をネットして収益額を表示しなければならないというのがあります。こちらは利益額には影響を与えませんが、計上する収益額が大幅に減ってしまう可能性はあります。
・減価償却
減価償却に関する基準差異はよく知られた論点かと思いますが、例えばIFRSでは定率法ではなく定額法が主流で、耐用年数も税法に基づくものではなく、自主的に決定した経済的耐用年数を使用するべき、といったものなどがあります。これについては影響が大きくなるかどうかは、保有する固定資産の内容や使用実態などにより会社ごとにケースバイケースで、ほとんど影響がなかった、という会社もあれば、非常に大きな影響を受けた会社もあり、一概には言いにくいものです。
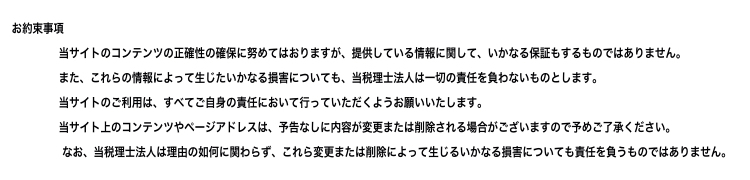
税理士法人セルボ・クレール
TOKYO OFFICE.
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-23-21 ヤマトハイツ802号室
TEL:03-6721-9737(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:03-6721-9738
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 長村 安展
公認会計士・税理士 渡邉 一生
OSAKA OFFICE.
〒530-0047
大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
TEL:06-6809-1664(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:06-6809-7664
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 木下 陽介
公認会計士・税理士 辻秀明