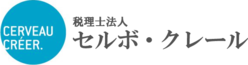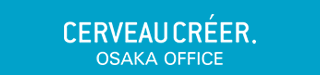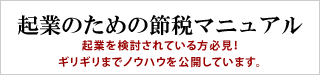転売目的で取得した物件の用途区分について
2017/09/01
用途区分の判定を行う時期について用途区分は課税仕入等を行った日において行う。当該用途区分が明らかでない場合に、課税期間の末日までに当該区分が明らかにされた場合には、その明らかにされた区分を適用することができる。また、合理的であると考えられる用途区分の判定を行った後で、実際には別の用途区分に使用された部分があったとしても、さかのぼって用途区分の判定をやり直して仕入控除税額の計算を修正する必要はない。
| 物件の賃貸契約 | 課税仕入に係る用途区分 |
| テナント、事務所賃貸のみ | 課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入(課税売上対応) |
| 住宅の賃貸のみ | その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入(非課税売上対応) |
| テナント、事務所、住宅の賃貸 | 共通対応 |
| 購入目的 | 物件の賃貸契約 | 課税仕入に係る用途区分 |
転売目的 | テナント、事務所賃貸のみ | 課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入(課税売上対応) |
| 住宅の賃貸のみ | 共通対応 | |
| テナント、事務所、住宅の賃貸 | 共通対応 |
- 物件の購入時に不動産の媒介契約を第三者と締結しておく
- 物件の販売広告をレインズに掲載する
- B/Sの販売用不動産(棚卸資産)に表示する等
(国税不服審判所の判例)住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例請求人は、本件各信託不動産(土地及び建物)に係る賃貸収入(住宅の貸付けに伴う賃貸収入)は、当該各不動産の取得に伴い付随的に生じたものにすぎず、当該各不動産の取得が当該各不動産の譲渡を目的とするものであることを妨げるものではないから、当該取得に係る課税仕入れは、消費税法第30条第2項第1号(個別対応方式)の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されるべき旨主張する。
しかしながら、請求人は、本件各信託不動産を、譲渡する目的だけでなく、その賃貸収入を得る目的を併せ持って取得したものであり、また、本件課税期間において、本件各信託不動産を取得した日から課税資産の譲渡等に該当しない当該各不動産に係る賃貸収入(住宅の貸付け)が生じている以上、本件各信託不動産に係る課税仕入れにつき、個別対応方式において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできず、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。
平成17年11月10日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/20/index.html
| 購入目的 | 物件の賃貸契約 | 課税仕入に係る用途区分 |
| 転売目的(地上げ案件) | テナント、事務所賃貸のみ | 課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入 (課税売上対応) |
| 住宅の賃貸のみ | ||
| テナント、事務所、住宅の賃貸 |
- 物件の購入時に不動産の媒介契約(売買予約契約)等を第三者と締結しておく
- 入居者の募集、契約更新を行わない
- 入居者に退去勧奨を行う
- B/Sの販売用不動産(棚卸資産)に表示する
- 減価償却を行わない等
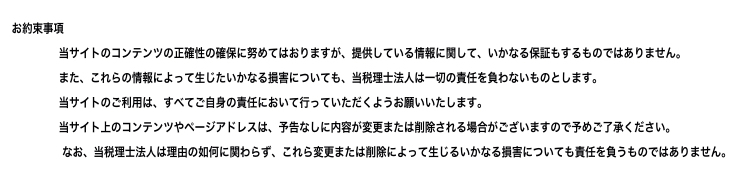
税理士法人セルボ・クレール
TOKYO OFFICE.
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-23-21 ヤマトハイツ802号室
TEL:03-6721-9737(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:03-6721-9738
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 長村 安展
公認会計士・税理士 渡邉 一生
OSAKA OFFICE.
〒530-0047
大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
TEL:06-6809-1664(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:06-6809-7664
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 木下 陽介
公認会計士・税理士 辻秀明