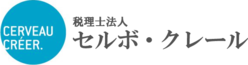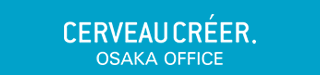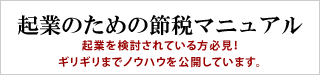特別縁故者(内縁関係)に係る相続税のまとめ
2017/08/31
| 条件など | 条文番号 | |
| 前提条件 | 亡くなられた方(被相続人)に相続人(配偶者、子、父、母、兄弟)がおらず、かつ、遺言書がないこと | 951条 |
| 要件① (①>②>③) | 被相続人と生計を同じくしていた者であること (いわゆる内縁関係にある夫婦や血の繋がりのない親子関係など) | 958条の3 |
| 要件② (②>③) | 被相続人の療養看護に努めた者であること (対価を得て行う介護ヘルパーや医師などは対象に含まれません) | 958条の3 |
| 要件③ | 被相続人と特別の縁故のあった者であること (師弟関係にあった方や非常に近しい友人など) | 958条の3 |
(遺贈により取得したものとみなす場合)第四条 民法第九百五十八条の三第一項 (特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項 に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
(民法:特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。(相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)
第二十九条 第四条に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
| 納税義務者 | 特別縁故者(相法1条の3、4条) 相続税法第4条の規定により特別縁故者は被相続人から「遺贈」により相続財産を取得したものとみなされます。 |
| 相続開始の日 | 被相続人が亡くなった日 相続税法第4条その他法令で特段の規定がなされていないため、相続開始の日は「被相続人が亡くなった日」とされています。従って、相続税の申告書の計算で用いる各法令や財産評価等の諸規定は、当該相続開始の日の法令を用いて計算を行うことになります。 例えば、H27年に基礎控除額や相続税の税率などが改正されているのですが、これらの計算は被相続人が亡くなった日がいつなのかに応じて計算を行うことになります。 |
| 相続財産の評価時期 | 家庭裁判所の審判が下りた日、ないしは、相続財産法人から相続財産の分与を受けた日と解釈されます(相法4条)。 個人的には家庭裁判所の審判が下りた日が適切なのではないかと思うのですが、管轄の税務署にて照会したところ相続財産法人から相続財産の分与(引き継ぎ)を受けた日を基準に時価評価するようにとのことでした。 |
| 相続財産の時価評価 | 相続財産法人から分与を受けた財産のうち、時価評価が必要なものについては、相続税評価額により時価評価を行うことになります(相法4条)。 相続財産法人が相続財産を換価(現金化)している場合、その換価されている相続財産について相続開始の日の各相続財産の細目に応じてそれぞれ時価評価すべきではないかという疑問が出てくるかと思いますが、結論としては、換価された相続財産については相続財産法人から分与された金額のままで問題ありません。つまり、相続開始の日の各相続財産の細目に応じて時価評価し直す必要はありません。 根拠としては相続税法第4条で遺贈により取得したものとみなされる相続財産とは、民法958条の3に規定する「清算後残存すべき相続財産」を意味しますので、換金等された財産についてはその換金後の財産を遺贈により取得したものとみなされるためです。 また、相続財産法人を管理する管財人弁護士に対する報酬等が分与を受けた相続財産から差し引かれている場合には、当該報酬を相続財産から差し引くことはできませんので注意が必要です。 |
| 申告期限 | 家庭裁判所から特別縁故者の審判が下りた日の翌日から10ヶ月以内とされています(相法29条)。 |
| 債務控除について | 特別縁故者は民法で定める相続人に該当しないため、債務控除の規定を適用することができません。しかし、相続税法基本通達で相続財産法人から弁済を受けていない葬式費用や被相続人の療養看護のための入院費用については、相続財産の評価額から直接控除することと規定されています。
|
| 3年内贈与財産の加算調整 | 特別縁故者が被相続人の相続開始前(被相続人が亡くなった日前)3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、当該贈与財産は相続財産に加算して相続税の計算を行う必要があります。 また、相続開始の年に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。しかし、特別縁故者となった方が相続開始の年に被相続人から贈与を受けていた場合には、一旦贈与税の申告を行い、後日特別縁故者の審判が下った後で相続税の申告に含めて処理し、過去に行った贈与税の申告については更正の請求を行うことになります。 この更正の請求を行える期限は特別縁故者の審判を受けた日(財産分与があったことを知った日)から4ケ月以内とされています。 ただし、生命保険金の受取人になるなどして相続税の申告を過去に行なっている場合には、相続税の課税対象として申告されているはずですし、3年内贈与財産の加算調整も行われているはずです。 (分与財産に加算する贈与財産) |
| 遺産に係る基礎控除 | 相続税の基礎控除額(相続税が課されない金額)は下記のように計算を行いますが、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には、法定相続人は存在していないことになりますので、相続財産の分与を受けた金額が下記の金額を超えている場合には、相続税の申告を行う必要があります。 相続開始の日が平成26年12月31日以前の場合 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(0人)=5,000万円 相続開始の日が平成27年1月1日以後の場合 3,000万円+600万円×法定相続人の数(0人)=3,000万円 |
| 配偶者に対する相続税額の軽減 | 配偶者が「相続財産の1/2まで」又は「1億6,000万円までの相続財産」を取得した場合には相続税が課税されないという制度なのですが、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には適用することができません。 |
| 相続税の2割加算 | 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(父、母、子)及び配偶者に該当しないため、相続税の2割加算の対象となります。 |
| 未成年者控除 障害者控除 | 民法に定める相続人であることが適用要件とされているため、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には適用することができません。 |
| 相次相続控除 | 民法に定める相続人であることが適用要件とされているため、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には適用することができません。 |
| 小規模宅地の特例 | 被相続人の親族であることが 適用要件とされているため、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には適用することができません。 |
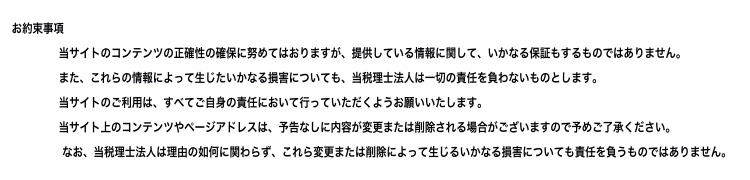
税理士法人セルボ・クレール
TOKYO OFFICE.
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-23-21 ヤマトハイツ802号室
TEL:03-6721-9737(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:03-6721-9738
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 長村 安展
公認会計士・税理士 渡邉 一生
OSAKA OFFICE.
〒530-0047
大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
TEL:06-6809-1664(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:06-6809-7664
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 木下 陽介
公認会計士・税理士 辻秀明