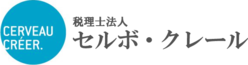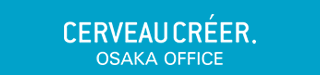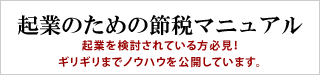土地を売却した場合の課税売上割合に準ずる割合の検討
2017/09/04
消費税法第30条③前項第一号に掲げる場合【個別対応方式を適用する場合】において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
一 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
二 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)
消費税法施行例第四十七条
法第三十条第三項第二号 に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項 に規定する課税売上割合に準ずる割合(以下この条において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号 ロに掲げる金額(次項及び第五項において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
3 税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
| 勘違いしやすい論点 | コメント |
| 課税仕入に係る消費税の計算方法の判定 (全額控除or個別対応方式/一括比例配分方式) | 課税売上割合が引き続き用いられます。
|
| 一括比例配分方式の計算でも使用できる? | 課税売上割合に準ずる割合は個別対応方式の共通仕入控除税額の計算にしか使用することはできません。一括比例配分方式では通常通り課税売上割合が適用されます。そのため、一括比例配分方式の強制適用期間中は個別対応方式を使用することができないため注意が必要です。 |
| いつから適用できる? | 課税売上割合に準ずる割合については税務署に承認申請書を提出し、署内での審査を受ける必要があるため、単に承認申請書を適用を受けたい課税期間中に提出しておけば良いというものではありません。審査には最低一月は必要となるため、余裕を持って申請を行い、税務署の担当者とも連携をとっておく方がベターです。 |
| 合理的な計算方法とは? | 消費税法基本通達では課税売上割合に準ずる割合の合理的な計算方法の例示や使用例が規定されています。
|
国税庁 質疑応答事例土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の1又は2の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を与えることとして差し支えないこととします。
1 当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合(消費税法施行令第53条第3項《通算課税売上割合の計算方法》に規定する計算方法により計算した割合をいう。)
2 当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
(注)
1 土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合とします。
2 課税売上割合に準ずる割合は、承認を受けた日の属する課税期間から適用となります。承認審査には一定の期間が必要となりますので、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、余裕をもって提出してください。
3 この課税売上割合に準ずる割合の承認は、たまたま土地の譲渡があった場合に行うものですから、当該課税期間において適用したときは、翌課税期間において「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出してください。なお、提出がない場合には、承認を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以降の承認を取り消すものとします。
| 適用要件 右記の三つの要件を満たす必要があります。 | 土地の譲渡が単発のものであること 質疑応答事例の趣旨から鑑みると、土地の譲渡が日常的に生じるような事業ではなく、質疑応答事例のタイトルにある通り「たまたま」土地を譲渡したような場合を想定していると考えられます。複数の土地の譲渡をした場合には適用できないのではないかとも考えられますが、同一用途で一体として使用されていた土地であれば問題はないように思います。また、例えば過去3年内に他の土地の譲渡があった場合については、税務署に個別に照会して判断をあおぐべきと思います。というのもあくまでこれは質疑応答事例でしかなく法令ではないため、事業の実態に応じた弾力的な運用がなされるはずだと考えられます。 |
| 事業者の営業の実態に変動がないこと 土地の売却が事業の清算活動の一環とみられる場合やリストラのために土地を売却する場合には注意が必要です。その売却した土地で行なっていた事業をやめてしまう場合や代替方法がないと認められる場合には、この要件を充足しない場合が考えられます。 | |
| 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること この過去3年間とは質疑応答事例の趣旨から鑑みて、土地を売却した課税期間を含めた過去3年間の期間を意味すると考えられますので、下記の点に注意が必要です。 ・直近の課税期間については、土地の売却収入を考慮せずに課税売上割合を計算する必要があります。 ・適用を受けたい課税期間の中途で課税売上割合を計算せざるを得ないため、直近の課税期間については土地売却後の最も新しい試算表に基づいて計算した課税売上割合を用いることになります。あくまで、土地の売却前後で事業の実態がないことが説明できれば問題ないと考えられますので、どの程度の期間を対象に課税売上割合を計算するのかは事前に税務署の担当官と打ち合わせておくべきと考えられます。 | |
| 計算方法 右記の課税売上割合の低い割合 | 土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合 |
| 土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合 | |
| その他 | 繰り返しになりますが、質疑応答事例に基づく課税売上割合に準ずる割合の適用はあくまで特例的なものです。従って、事前に税務署の担当官とすり合わせを行うべきです。また、承認申請書の様式も上記の適用要件や課税売上割合の比較計算を行うようになっていないため、参考資料等を添付しておく必要があります。また、そもそも論ですが、課税売上割合に準ずる割合が影響するのは課税仕入の用途区分が課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものに共通して要するもの(共通対応)に区分されるものに係る消費税についてだけですので、共通対応に区分される課税仕入の金額があまり大きくない場合にはほとんど効果がないといったケースも考えられます。 |
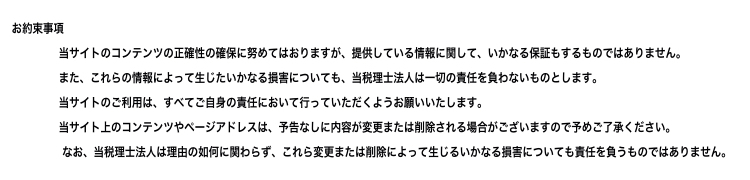
税理士法人セルボ・クレール
TOKYO OFFICE.
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-23-21 ヤマトハイツ802号室
TEL:03-6721-9737(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:03-6721-9738
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 長村 安展
公認会計士・税理士 渡邉 一生
OSAKA OFFICE.
〒530-0047
大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
TEL:06-6809-1664(営業時間:9:30〜18:30)
FAX:06-6809-7664
Mail:info(a)cerveau-creer.com
代表社員 税理士 木下 陽介
公認会計士・税理士 辻秀明